阿多野新田の開発
吉久保をすぎて阿多野のバス停のちょっと先に大きな石碑があります。この碑は江戸時代(1672年)にこのあたりの荒れた様子を見て田を開きたいそのためにはここまで水を引いてこなければならない。用水を引こうと考えその事業に尽くした池谷市左衛門をたたえるために立てられたものです。 |
須川の南に広がる「アダノッパラ」と呼ばれる台地、阿多野は昔、田んぼなどまったく無く荒れた荒野野でした。今から約300年前(寛文8年・1668年)湯船村(今の小山町湯船)に住む池谷市左衛門は、この荒れた土地を見て何とかして田を作るようにしたい。そのためには水が必要だ。何とか水を引きたいものだと考えていました。
|
あるとき、江戸見物に行った湯船村名主(池谷)市左衛門は旅の疲れを癒すためにある店に入りました。酒を飲んでるうちに前の方に座っている男と友達になりました。市左衛門はこの男と話がはずんで、自分の住んでいる村の事や、今一番やりたいと思っている考えも話して聞かせました。すると、男は大変心を動かされ、「反れこそ男の仕事だ男に生まれたからには一生のうち一度はしてみたい大仕事だ。」と共感され、どうか私にも手伝わせてはもらえないだろうか。と言うのです。
市左衛門は江戸見物のみあげがこんな大きなものになるとは思っても無く二人はてを握り合い意気投合しました。そして、田に水を引く計画はとんとん拍子にまとまりました。この男こそ、阿多野用水を作るためにお金を出し、工事の計画に力をかしてくれた江戸材木町石屋(喜多)善左衛門だったのです。 |
| 寛文8年工事を始める許可を小田原藩に出しました、箱根用水は3年も許可が下りなかったのに阿多野用水は直ぐに開発請負人として許可がおりたのです。これは、新しい田を開発する事業に前向きな徳川幕府の政治にあっていたからです。そして、箱根のような重要な道からは外れていたので関所破りという疑いもなかったのです。 |
| 寛文8年3月 阿多野新田開発の基本工事はまず、善左衛門はそのあたりを測量して阿多野原へはどこjから水を引いてきたらよいか考えました。今のような測量機器がなかったので、暗くなるのをまってたくさんの人にちょうちんを持たせ山や林に並ばせてその明かりをたよりに高さ、低さを調べました。同じ間隔に並ばせて距離も知ることができました。 |
いよいよトンネル工事にかかりました。水源は大御神の布引滝を数町下った大御神村と棚頭村の境あたりに長さ50間横32間の溜池を築いた。現在大御神堤と称されているのがそれである。そこに縦一丈横八尺の水門を設けて八間余りの大きな樋を架け、 その下からサイフォン式にして用水へ水を流し出す工夫をしました。(用水路の落差が少なかったので水に勢いをつけさせるためと枯れ枝や土が水路につまらなくするため)
用水路の長さ(約10,765メートル)、全水路のうち1400メートルの5つのトンネルは、大御神・中日向・棚頭を通り現在の国道246号の手前に出て川となっています。そして、吉久保の一部、阿多野へと流れていきます。
北善左衛門に雇われ大勢の人が働き毎日トンネルの中に水神さんを祭って怪我のないように、早く工事が進むようにと拝みました。トンネル堀はところどころに穴をあけました(5箇所)掘り進んだ石や土を出したり空気を入れる役割をします。また、煙を出したりして工事をしている場所の確認もしながら掘り進んだのです。この穴は工事が終わった時埋め戻されましたが、今でも年に一度の掃除の時にはその穴のあとがはっきりとわかります。また、油を燃やして明かりにしただろうと思われる明かり置き台のあともわかります。
硬い岩にぶち当たるとサトイモの茎の干したものをいっぱいそばにおいて一晩燃すことで次の日には岩は少しもろくなってたたいて壊す事ができました。トンネルの外では用水路を作る仕事が次々と進んでいました。
|
このようにして、多くの人たちの努力で工事もはかどり約3年半のうち、寛文12年12月に完成しました。費用は当時のお金で9000両、今のお金で約9億円ぐらいかかったそうです。
善左衛門は惜しくもこの年病気で亡くなってしまいました。
その後、元禄16年(1703年)の大地震と、続く宝永4年(1707年)の噴火(富士山)があり、新田村落としての成立間もないこの村に甚大な被害を与えるこことなった。トンネル(1300間余)が崩落し、埋められてしまいました。そこで早々その翌年から修覆工事に善左衛門の息子の長十郎が10年もかけて用水路を復旧しました。この時の工事費には2500両という莫大な費用がかけられた。この工事は放映4年10月に完了し水路が通じる事となったが、それもつかの間、同年11月の宝永の大噴火によって用水路は2・3mもの火山灰で埋まってしまった。村民たちは砂を取り除く作業に多大なエネルギーを費やした。享保6年に至っても36石の村高のうち24石余は砂埋り地という有様であった。この人夫もあまり多くなかったので、「村鑑」には「百姓因窮仕候」と記されている。
|
田の開けた阿多野に他の村から人が移り住むようになりました。この人たちの中には工事で一生懸命働いた人がいます。その頃、17家が水の権利を持っていました。苦労して引いた水を無駄にしないでいろいろな決まりを作り大事に使っています。
よその部落へはいらなくなた水を流します。用水の途中からは五合枡の大きさの水の取り入れ口、と
決めて阿多野用水路から、『いづみや堰水』として、吉久保に譲っています。 |
| 阿多野用水ができて開けた田は |
阿多野26町歩(1町=10反)
菅沼17町歩
吉久保7町歩
水を引いた阿多野はいっぺんい北郷の米どころとなり、秋には金色の稲穂が波うちました。今では水田も倍に増え、冬には水田の裏作として、『水菜』を作っています。この水も水利権のある決められた農家でしか使う事ができません。 |
|
| 小山町資料より |
|
|
|
| 年1回の用水路を干した状態路の |
|
|
 |
|
|
1年に一度、用水路の手入れをするために左側の放水門の水門を明けて用水路の水を止めます。めます。 |
用水路を須川に放流すると堤池の水量も減ってしまう。写真の左側から水門へとサイフォン式に取り入れる。 |
用水路に水を流しているときは池にも水が満ち溢れている。 |
|
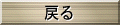
|

